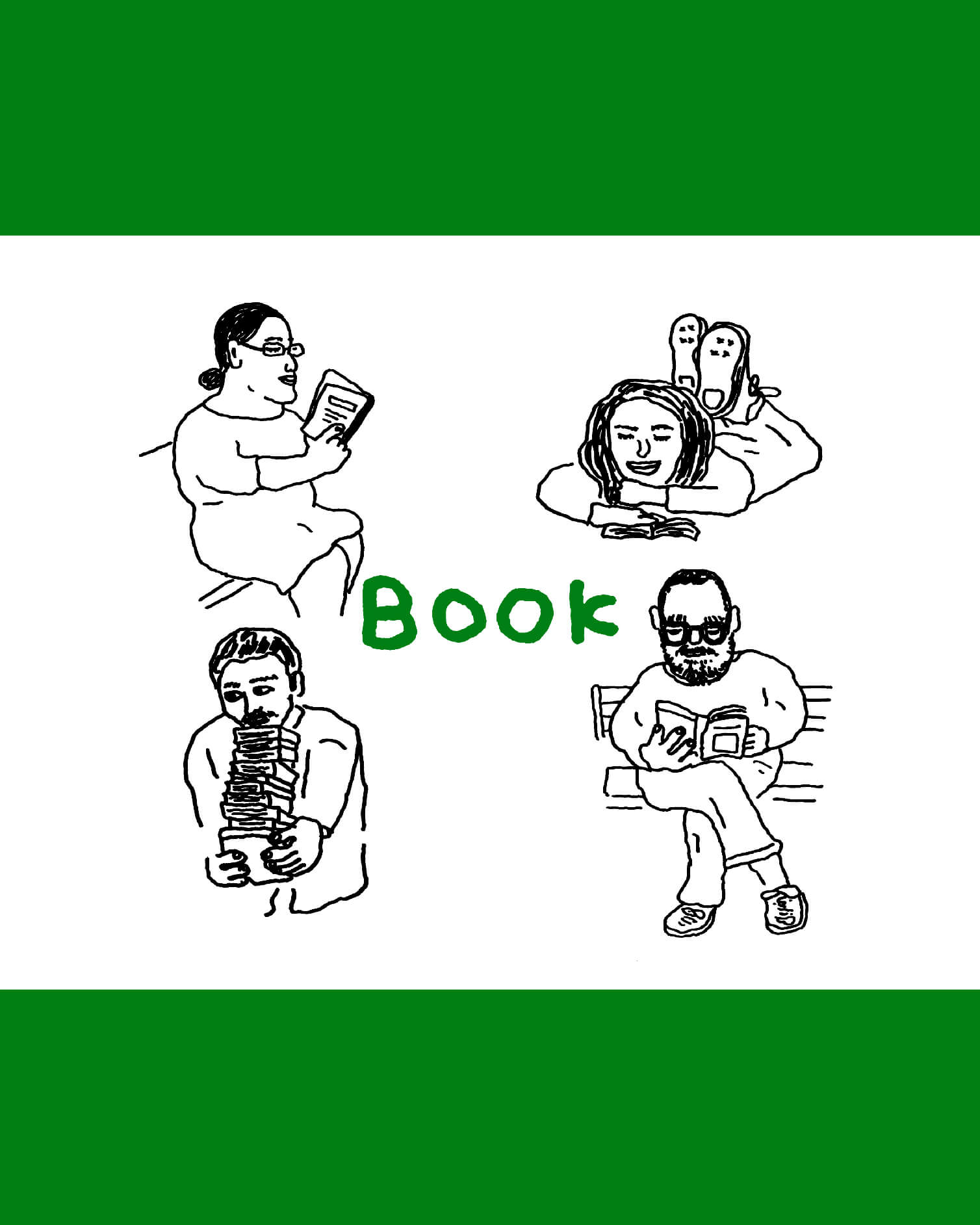ハイウェイを走るユニークな車とドライバーを並走して撮影した写真集『Los Angeles Car Club』(Los Angeles,USA)
平野太呂さんは「バンドのノベルティのような気持ちで」フォトTシャツを作り始めた。淡々と手を動かし続けることの美徳を知っている太呂さんは、今、何を考えているのか? クライアントワーク、作品撮影、双方のために多く旅をしていた写真家に聞いた。
ステイホーム
遠くへ出かけられない時間
——どこか遠くに写真を撮りに行っていた太呂さんは、写真を捕まえに行く、という感覚だったのでしょうか? 旅に出れなくなった状況で、今度は自分の身の回りを撮影するようになるのでしょうか?
この状況で何ができるかについては、僕も全然、結論出ていないけどね。フォトグラファーにはざっくり2タイプいて、身近な家族を撮ることが作品になる人もいれば、誰も見たことのないものを見つけてきて撮る人もいる。僕は7対3で、出かけていくタイプだと思うけど、辺境とか、ほとんどの人が行けない場所に行くわけでもない。心のどこかで自分の身の回りのことを撮って、何かしらまとめなきゃいけないんだろうなっていう気持ちはずっと持ち続けているんだよね。今は嫌というほど家族と一緒にいて、何か変わるかもしれないと思いつつ、今のところ何も分からないよね。

アメリカ西海岸の住宅地で、スケーターたちの滑り場となっていた空っぽのプールを撮影した写真集『POOL』(California,USA)
——太呂さんはアメリカの西海岸に行っても使われていない家のプールを撮影したり(『POOL』)、ハワイに行ってもスケートスポットの排水溝を撮影したり(『I HAVEN’T SEEN HIM』)、例え観光地であったとしても、いつも人とは異なる視点で写真を撮っています。その視点で日常生活を眺めてみる、という試みをしようと考えているのでしょうか?
そう、だとは思うんだけど、やっぱり日常を一連の作品にするっていう「脳みそ」は、毎日のバタバタの中では残らないんだよね。どこか出かけたときに、そういう「脳みそ」になるっていうことがやっぱりあるんだけど、でも、旅先だけが僕の人生じゃないし、むしろ家にいる時間の方が人生の大部分だったりする。それをどうにかまとめて、、、というか、残しておきたい気持ちはあるんだけど、そのまとめ方がまあ難しいよね。
今は時間があって、いい機会すぎるから、フォトグラファーとしてこの期間中になんとかしなくちゃいけないんじゃないかっていう焦りもある。強迫観念的なものがね。それは例えば東日本大震災のときに、僕なりの視点で何かを発しなきゃいけないんじゃないかって思ったのに似てる。結局、あの時はアイディアが出なかったし、なにもやらなかったけれど、そういうのに似てるかな。
数ヶ月間何もない、家族とだけ過ごす時間で、ましてや今回は東京が現場になっているから。そこで何か撮らなきゃいけないんじゃないかって思っちゃう。
——でも、現実的に発表のために何かを模索しているわけではないと。
そう。無理に写真を撮らなくてもいいっていう気持ちもどこかにあって、何かあるごとに、自分の考え方を発表しなくてもいいんじゃないかなと。その時に合ったものをできていれば精神的に健康だし、いいなと思う。それが写真じゃなくてもね。移動できなくても自分の精神が穏やかになるところを見つけて、そこにフォーカスしながら過ごせるんだなって気づいたし。
新型コロナウィルス感染症って、自分が無症状の感染者だと気づかずに人にうつしてしまうかもしれない。なんて言うか、すごく特殊な“縛り”がある状況でしょう? 僕が何をしているかっていうと、近所の河原に行って、そこで子どもたちと遊んでる。昨年の台風19号で泥を被っちゃっていたのを、以前にも散歩してたから知ってたの。たまたまボランティアのおじさんから湧き水があるっていう話を聞いていたから、ひたすらそこで泥をかき出して、流木を整理して、土木工事してる(笑)。息子たちも楽しくなっちゃって、スコップ持たせると黙々と掘ってる。何かをしなさいって言わなくても、何もルールもないところで、自分でやれることを見つけてて。それがすごく楽しい。
それを写真で表現したいっていうのはやっぱり違うなって。


自分の足元にあった、
価値あるものを探し直す
——現実的に雑誌の撮影など、クライアントワークも停止しています。仕事での撮影に関しても、変化がありますか? フォトTシャツのブランド〈grosso〉を始めたのも、新しい動きの一つですか?
写真一本で! って心に決めたわけでもなんでもなくて、頼んでくれる人がいるから、ここまでやってきただけだから。10数年続けていたギャラリーは一旦やめているけど、僕はやっぱり仕事は2、3個あった方が、潰しが効くんじゃないかと思ってる。年齢を考えてもいつまでも仕事があるわけないし、考えなきゃいけないなって思っていたところにこの状況だから、本当にそうなんだな〜って。
それで、今できることなんだろうと考えて、バンドがライブハウスでTシャツを物販するみたいな感覚で、Tシャツ作ってみてる。でも、違う仕事を始めたとしても、それで写真をやめるわけではないけどね。

エルヴィス・プレスリーなりきる人々を撮った写真集『The Kings』(Memphis, USA)
——自分がどうやって金銭を稼いできたのか、何を食べているのか、どういう場所に住んでいるか、足元を見つめ直すきっかけになっていますよね。
うん。それはやっぱり震災の時に自給自足してうまくやっている人たちを見て、すごいなと思ったけど、自分はそうはなれないっていうこともわかってる。だから街中に住んでいるなりに、自分が落ち着くポイントを見つけ出していく。それは、ハワイに行っても海を撮らないで、排水溝を撮影しているのと同じようなものかもしれない(笑)。
誰もここ来ないでしょっていう場所を見つけられる。この状況で、この縛りがあって、それならここがいいみたいなものを見つけられる感覚を、僕は気に入っているんだよね。
——太呂さんの作品にも通底する感覚かもしれません。写真は旅先で撮ることが多くても、旅先でも日常でも、ある条件の中で何かを見つけ出す感覚はあまり変わらないと。
例えば地方ロケにクルマで行ったりすると、帰りにGoogleマップで水のマークを探して、見に行ったりしていたの。水辺を見ていると落ち着く性格だと思っているんだけど、そういう無意識に感じていたことが、実は近所に河原があるっていう今住んでいる場所にも繋がっていて、その自分の選択によって自分が助けられるみたいなことはあるかもしれない。無意識だったことが、この状況で表面化するような。旅で得るものと同じような価値のものをじっくり探すチャンスだろうなとは思ってる。近くにあるものの方が見えづらいから、難しそうだなとは思ってるけどね、なぜなら、もうすでに見ているものだから。
旅から受ける刺激とは違うものだけど、何か似ているような気がする。
——それが見つけられたら、作品として発表できるかもしれない。
そう、それをしなきゃいけないって思った。旅は通過していくものだから、点と点でぶつかる瞬間でしかない。でも定点観測ならば、変化とそのきっかけがわかる。ゆっくりだけど実はすごく動いていたり、変わっていたりすることがわかるんじゃないかな。結局、どんな場所に行っても、旅先ではよそ者のマインドで、よそ者の自分を楽しんでいるんだよね。
僕の作品はいつもそうだけど、現地に住んでいる人には見えないことを、よそから来た僕だから見える部分をテーマにしている。それが旅の基準というか、旅の面白味だと僕は思ってる。なんかこの看板、現地の人は普通にしているけど、おかしいよ、みたいなものを見つけるのが好きだし、見つけちゃう。そういう視点を持つのが気持ちいいっていうか。
でも、それが自分のホームタウンでできなきゃダメじゃないかってちょっと思ってたわけ。今は、誰も見向きもしない湧き水を掘り出して充足しちゃっているけどね(笑)。

「ワローズ」と呼ばれるハワイの排水溝を撮影した写真集『I HAVEN’T SEEN HIM』(Oahu, Hawaii)
平野太呂
写真家。1973年生まれ。武蔵野美術大学映像学科卒。2000年よりフリーランスとして活動を開始。スケートボードカルチャーを基盤にしながらも、カルチャー誌やファッション誌や広告などで活動。2004年から2019年までオルタナティヴなスペースNO.12 GALLERY主宰。多くのインディペンデントな作家達が展示をする場所となった。主な著書に『POOL』(リトルモア)『ばらばら』(星野源と共著/リトルモア)『東京の仕事場』(マガジンハウス)『ボクと先輩』(晶文社)『Los Angeles Car Club』(私家版)『The Kings』(ELVIS PRESS)『I HAVEN’T SEEN HIM』(Sign)がある
tarohirano.com
Photo by Taro Hirano Text by Toshiya Muraoka