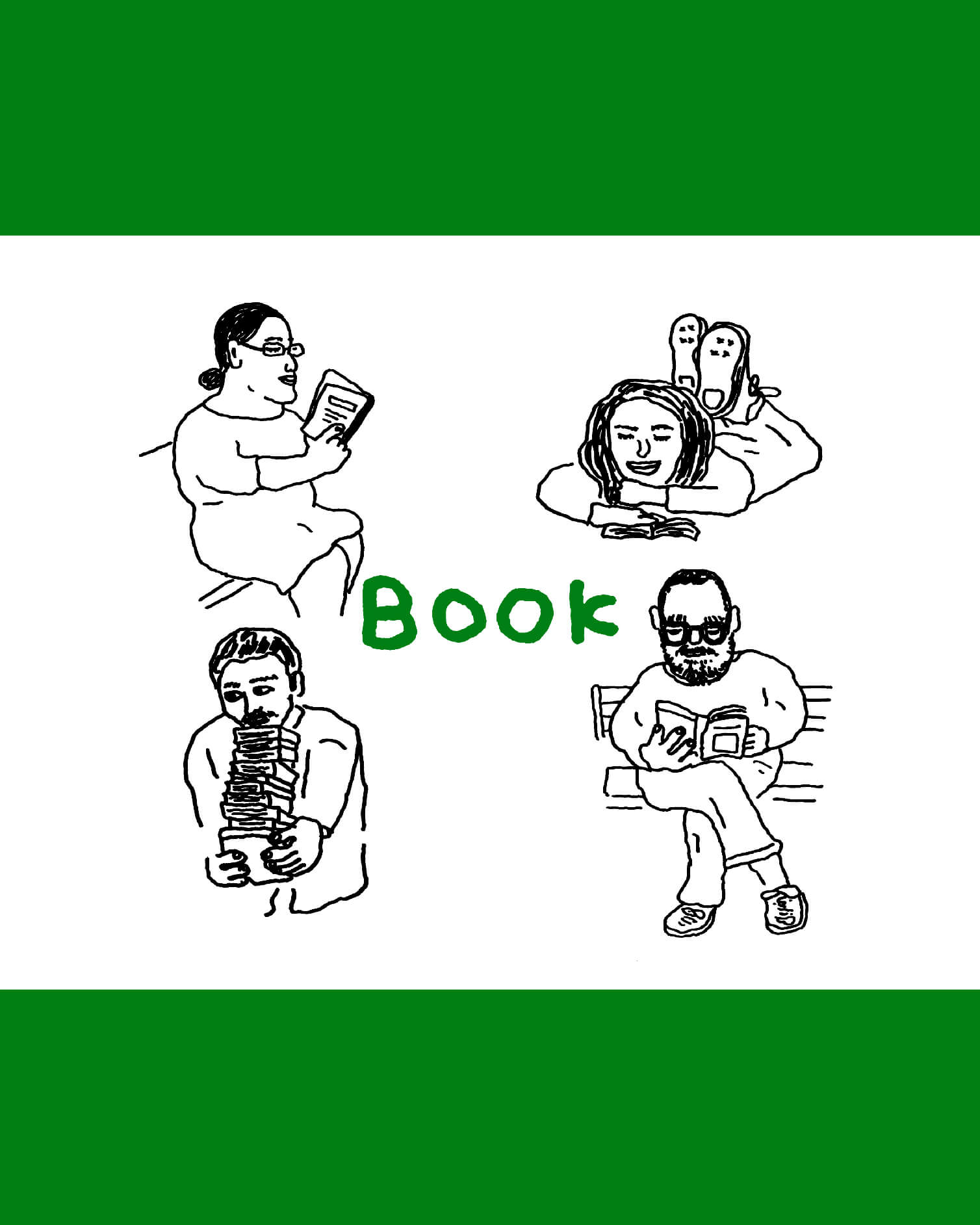写真は撮らずに毎朝走ってた
——日本から出ることのできなかった今年の春には、どうやって過ごしていましたか?
2月の初旬からパキスタンに遠征に行って、帰って来た途端にコロナ禍でどこにも行けなくなってしまいました。予定では帰国後すぐにパレスチナのガザ地区に行くはずだったんですが、それもなくなって。そのあとのスケジュールは全て白紙になりましたね。


自粛期間中は、毎朝4時に起きて、多摩川沿いを走ってました。体力つけるために。人がいない時間と思って早朝に走ってたんですけど、それは旅している時とほとんど同じスタンスだったんですよね。毎年通っていたネパール、パキスタンにいると、外で写真を撮るのは朝と夕方って決めているので、必ず早起きなんです。昼間は光が強すぎるので、室内の撮影に回しているんです。仕事もなかったので、まるで海外で旅をしているような、自由に過ごしているような感覚でした。自分はルーティンを刻めるタイプなんだなと改めて思いました。

——(コロナ禍に見舞われ、国内に長期いたために)久しぶりに桜を見たとおっしゃっていましたが、これまで東京の春を撮ろうとは思わなかった?
今回の自粛期間で一番わかったことは、自分はほとんどスナップを撮りに行ったりしないんだなっていうことですね。普段、日常で起こっていることをあんまり撮らないんだなって。いや、撮ってはいるんですけど、作品意識がないんです。自分はいつも、何かを伝えるためのツールとして写真を捉えているというか。

例えばガザに行こうと思っていたのは、3月11日に日本の東北に向けて凧揚げをするっていう企画を記事で見つけたからなんです。ガザ地区っていう閉鎖された中で、日本に対して想いを届けるって、すごく素敵だなって思って、取材が入るという話もなかったので、それならば自分が撮ったらもっと広められるんじゃないかなと。それで撮りに行きたかったんですね。結果的には行けなかったわけですけれども。
「撮ること」と「思い入れ」の関係性
——ライフワークのように、ネパールやパキスタンに通っているのはなぜですか?
僕の今までのテーマって、ほぼすべて友達から始まっているんです。例えばネパールは、大学生の時にパリのコレクションの撮影をしていて、金銭的にずっとパリに滞在することはできないので、滞在費が安い国を探して、ギリギリまでそこに滞在して、パリの仕事に戻るっていう暮らしをしていて。ネパールの山小屋は家事を手伝ったら、宿代タダっていう話を聞いて、大分長い時間を過ごしていました。そこでネパール人の友達ができたから撮影に通うようになった。

当時、インドのコルカタなどのスラム街にある「少女奴隷」のことを知って、これはどこから始まっているんだろうとずっと探していたんです。それでネパールのニムディーっていう村にたどり着いた。その村には通い出して、今年で5年目なんですけど、きっかけも、たまたまその村の子たちと仲良くなったから。大学生の頃から気になっていた「少女奴隷」の問題と、たまたま知り合った子たちが重なったというか。

——自分に近いものとして問題を捉えることができれば、撮影に赴くようになると。
はい。だからタイムリーなドキュメンタリーって自分はあんまり撮ってないんです。今回もコロナの禍中にいて、自分はこういうの撮ると思っていたのに、実際のその状況になってみたら撮ってなかった。
簡単な言葉でまとめてしまうと「思い入れがあるところは撮りやすい」っていうことなんだと思うんです。ネパールには毎年3月に行くんですけど、ヒマラヤに入って下りてきて、そこからニムディー村に行くのが1年に一度のご褒美になってます。ニムディーに行く時には、日本から化粧品や洋服を集めて持って行ったり、去年は電信柱つけたり、テレビを取り付けたりして、なんだか実家に帰るような気持ちになるから楽しんでいたんです。今年も村の人たちからメールが来るんですね、「来ないのか?」って。実際に行けなくなって思うのは、「行きたい」っていう当たり前のことなんです。
パキスタンを取材していた時には、アフガニスタンの難民キャンプに行きました。外国人は基本的には入れない場所なんですけど、ひょんなルートから入ることができて。まずゴミ箱がない。衛生最悪。家も泥で作られているから崩れて人が死ぬなんて当たり前で。

数ヶ月前にペシャワール会の中村(哲)先生が殺されてしまっていたから、「日本人の君がここに来たっていうことは、次は君が支援をしてくれるのか」って言われました。学校や病院を作ってくれって。「僕はフォトグラファーだから、今の状況を伝えることはできるけど、学校を作ることはできない可能性の方が高い」っていう話をしたり。ゴミが捨てられためちゃくちゃ汚い川で子供が遊んでいて、これはどうにかならないの? って言ったら、「ゴミ収集車だってこないのに、お前は簡単にそんなこと言うな」って怒られたり。こちらはアイディアを出しただけだよっていう話をしたんですけど、正直、日本に帰ってきた時には「きつい」としか思えなかったんですね。もう海外は当分行きたくないって。でも今は、行きたいんですよね。きつくて辛かった現地の難民キャンプにも、やっぱり今は行きたいんですよ。

作品のために貧しい村を撮りたい訳ではない
——フォトグラファーではなく、病院を建てる人になろうとは思わない?
俺は、そういうふうに思っちゃうタイプだったんですけど、人にはできることとできないことがあるっていうのを、ようやくわかってきたというか(笑)。ネパールの村の子どもたちに電信柱を作ってって言われたら、作っちゃうんです。でも、すべてができるわけじゃないから、自分には何ができるのかを明確にするっていうことを今年は考えなきゃいけないと思ってます。自分にできるのは、徹底して何かを伝えること、人をつなげることなんじゃないかって思っています。
——その伝え方に、今後はより注力していくという思いに至ったんですね。
そうですね。パキスタンにあるアフガンの難民キャンプでも、ポートレートをたくさん撮らせてもらったんです。写真集を作ろうと思えば作れるくらい。でも、もし写真集を作るためにその村に行ってたら、その人たちはどういう思いで写真を撮られるんだろうって考えちゃいましたね。なんていうか、自分の作品として発表するためだけに難民を追うとか、貧しい村を追うって、どうなのかなって思います。
ただ、伝えるための手段として作品があって、それがどんなメディアであったって構わないんじゃないかとも思うようになりました。真実は一つじゃないんで、日本人である僕から見た写真、それを考える題材として見て欲しい。新聞記者ではない自分にできるのは、そういうことなのかなと思うようになりました。

被写体にとって「自分は撮って良い存在」でありたい
——一度、立ち止まって考える時間を持つことができたと。
あまりにも忙しかったんだなって気づきました。その忙しさが、自分を成長させてくれたっていうのは事実だなと。その上で、写真の基礎として、自分が意識しているのは、相手にとって「撮って良い存在」になれるかどうか。ネパールのニムディーにしても、2年通って仲良くなってからじゃなきゃ「撮っていいですか?」って聞けないんです(笑)。要は空気を読まない人には、僕は勝てないかもしれない。
気になる女性が歩いていたとして、パッと撮りたいんですけど、でも嫌な思いをさせたらって思ったら撮れない。そこがずっともどかしくもあったんですけど、仕事も含めていろんな撮影をしていく中で、その人にとって自分がいかに「良い存在」になるのか、常に修行してるんだなと思ったんです。
かつてスティーブ・マッカリーという写真家が、『ナショナルジオ・グラフィック』でアフガンの少女の写真を発表してすごく有名になりましたけど、その少女は20年後に取材されたときに、当時写真を撮られるのがすごく嫌だったと言っていて。個人的には大好きな写真家で、とても影響を受けているんですが、僕は、その人が望んでいないのに写真を撮るのはどうかなって思ってしまうんですよ。そのスタンスだともちろん撮り逃がすこともありますけど、でも、喜んでくれるから撮りたい。そのすごく微妙なところを洗練していかないといけないんだなと思います。
だから、この海外に行けない状況だと、あのときの1秒1秒をもっと掘り出せばよかったと思います。


「金を送ってくれ」インドの知人からの連絡
——移動を止めざるをえないから気づかされることも多いんですね。
あ、それから相談なんですけど、インド人の知り合いから、家族に食わす金がないから、金を送ってくれって言われたんですけど、どう思います? 俺だって何ヶ月も仕事していないのに、ここで金をあげるのかと。海外で金くれよって散々ある話だから、自分なりにルールは
決めてたんですけど、今回はリモート過ぎて判断が難しくて。そのインド人とは一度しか会ったことないし、むしろより関係性の深い人に渡すべきなのかなとも思うし。旅の時にはいつも、騙されようが痛い目を見るのはこっちだったらいいかって思ってるんですけどね(笑)。
——阿部さんは、常に弱者の側に立つというか、自分の旅に対するスタンス、被写体に対する考え方が明確にありますね。
いや、あんまりトゥーマッチに考えすぎないように、こちらが潰れない程度に、気楽に付き合っていこうと思ってます。でも、この考えまくる2ヶ月間で、やっぱり旅に「行きたい」っていう気持ちが再確認できたんで、自分の目線で、これからも撮り続けて行こうと思っています。

阿部裕介
1989年東京生まれ。写真家。青山学院大学経営学部修了。大学在学中より、アジア、ヨーロッパを旅する。在学中、旅で得た情報を頼りに、ネパール大地震による被災地支援(15年)や、女性強制労働問題「ライ麦畑に囲まれて」や、パキスタンの辺境に住む人々の普遍的な生活「清く美しく、そして強く」を対象に撮影している。日本での活動としては家族写真のシリーズ「ある家族」がある。
yusukeabephoto.com
yardtokyo.com
Photo by Yusuke Abe Text by Toshiya Muraoka