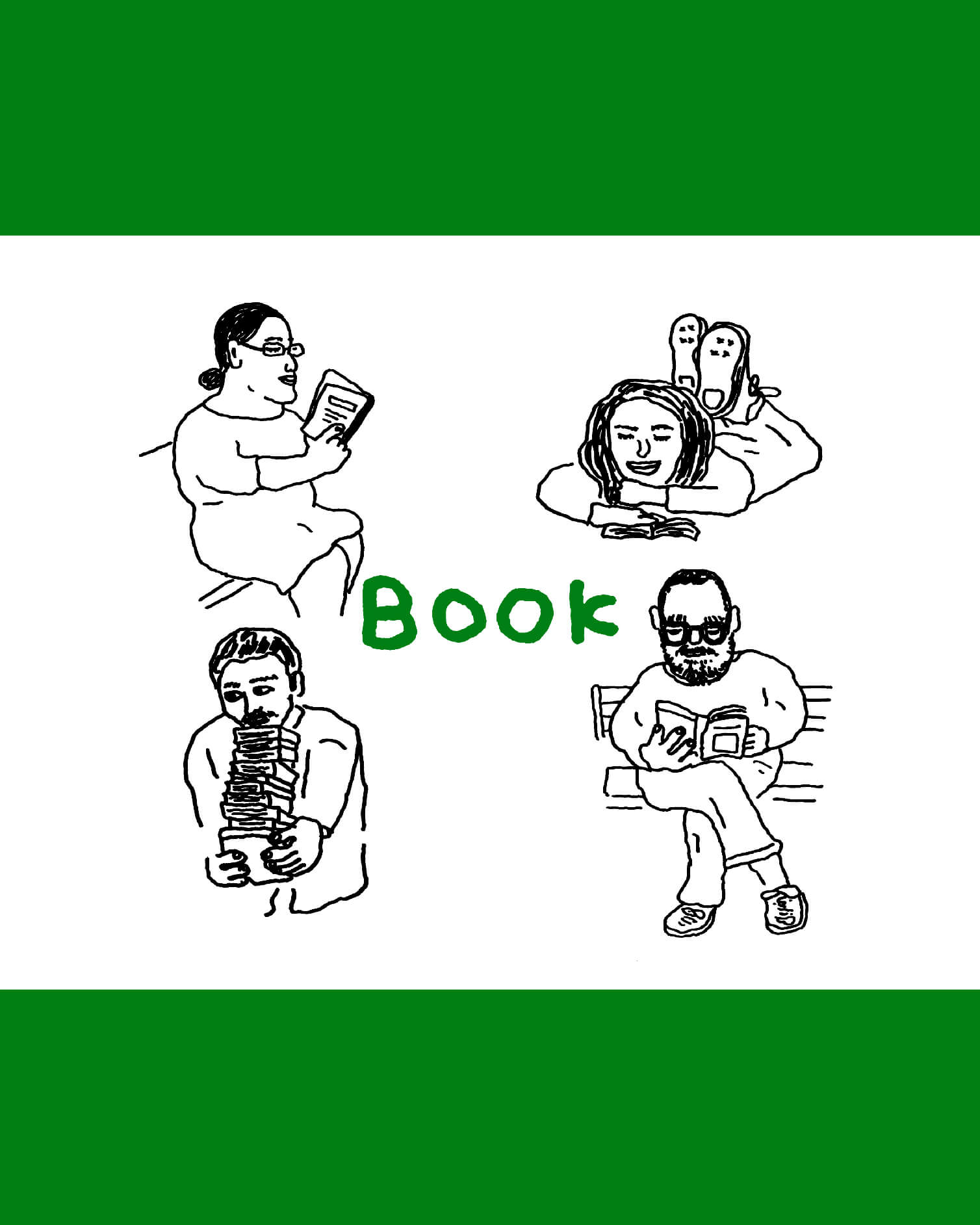バンに住みながら作品を発表してきた
——コロナ禍によってライフスタイルは変わりましたか?
毎年、春先から夏の前後までは、祖母の世話をするために日本に帰ってきていたんです。今年は事態が急変していった2月の2週目あたりに大阪に帰ってきて、4月後半に祖母を看取って、その後もずっと日本にいます。
大阪にいるときはいつもサーフィンを頭に入れていなくて、祖母と一緒にいながら経理周りの整理整頓をしていたんですね。今回はアメリカにも戻れないし、予定が立てられないので、もう一回、自分の中で今まで手をつけていなかったことを積み重ねておこう、みたいな感じで時間を使ってますね。

——経理周りだけでなく、自身のプロジェクトを見直す時間でもあったと。
自分の中の整理整頓ってことですよね。頭の中をクリーンにして。僕が今までにやってきたプロジェクトって、ものすごい時間がかかってるんですよ。2018年に写真集『Authentic Wave』を出したんですけど、完成までに20年かかってるんです。それがいいか悪いかという話ではなくて、たまたま時間がかかってしまっただけなんですけど、僕はそれぐらいのスパンでやってきてる。新しいプロジェクトにしても、同じくらい時間かかってもいいかなとのんびり構えているんですけど(笑)。それくらい作り込みたいプロジェクトが2つ3つあるんです。今回の空いた時間で、ようやくそっちにシフトできるかなと。考える時間ができたんで。
——竹井さんの制作には、どうしてそれほどの長い時間が必要となるんでしょう?
僕はアメリカの大学の写真学科を出たんですけど、テーマを自分で育てていく方法を習っているんですね。テーマって、そこら中にあるかと言ったらそんなことなくて、自分の主題って実は1つか2つしかない。それを徹底的にやるんだって学校で教わっているんで、時間がかかるのは当たり前というか。常に頭の片隅にその主題を置きながら、時には遠回りすることも必要だったりするんです。日常的にはまったく違うことをしながら、またそこに自分を近づけていくっていうんかな。仕事としてサーフィンの動画を撮影している間にも、頭のどこかでプロジェクトのことは考えている。

——新しいプロジェクトも、サーフィンを軸にしたものであることは変わらないんでしょうか?
そうですね。それがやりたくてアメリカに行ったし、クルマの中に住みながら撮影してっていうことも、当時は誰もやっていなかった。僕は、写真集っていう目標があったからやったんですけどね。次のプロジェクトには、そこまで「これでないといかん」っていう確固たるものはないですけど、やっぱりサーフィンが拠り所としてあって、進めていけるかなとは思ってます。
16mmフィルムの映画を撮りたいと思っているんです。なぜかというと、人間らしさがあるっていうか。昔、僕らの祖父母や両親の世代には当たり前にやっていたことが、僕らの世代で失われている途中で、でもまだできる。だから、やっておきたいんです。ただ、それにはお金も時間もかかるなと。

16mmフィルムの質感
——大阪にいるときには、サーフィンはしないと、自分の中でルールを決めているんですか?
大阪では違うことに集中して、アメリカに戻って写真とサーフィンって、はっきり分けているところはありますね。自分のルールに従ってやると、しんどいけれど、「ここまでいける」っていうのがこの歳になってわかってきてるから(笑)。
今、具体的に何をしているかと言うと、日本語で言えば脚本になるのかな、いわゆるスクリプトを書いているんですね。昔、アメリカで大学に行っていたときにスクリプトの書き方の講座をいくつか受けていたんで、その時のノートを見返しながら、あの時受けといてよかったなと(笑)。当時は理解できていなかったり、やれてなかったりしたことが、こうして今、時間はかかっているけどきちんと向き合えている。だから、この先の見えない間も、いい時間の使い方やなって思ってるんです。
文章書かなあかんし、本もたくさん読まなあかんし、映画もいっぱい観なあかんから。当時の先生に出された映画リストを片っ端から観てたりしますね。それはサーフムービーに限らず、ゴダールからウッディ・アレンから昔のフランス映画みたいなものまで。だから、書いては止まって、また観て読んで、また書いて止まって、みたいな日々です。
——この時代に16㎜で映画を撮るモチベーションは、他に誰もやらないから、というものですか?
目立ちたいとかではなくて、こういう事をやれる最後の世代になるんやろなって思ってるんです。僕は16mmを実際に観て、その質感、リアルさみたいなものを知っていますけど、僕らより下の世代は、いきなりビデオで始まっていて、それが映像だと思っている。そこに穴を開けるというか、細い糸を垂らすみたいな感じかな。その糸に引っかかってくれる人は僕の世代だけでなく、若い人にもいるはず。テクノロジーとか、デジタル技術に対して、一度、立ち止まって考えたいみたいな感覚はあるんですよ。
僕が学生時代に習った写真は、自分の撮った36枚撮りのネガを徹底的にルーペで見て、それからプリントに起こすんですよ。暗室に入って、先生に批判されて、8X10インチの印画紙に焼いて、クラスで発表して、みんなの意見をもらって、また暗室に帰る。だから、えらい時間がかかるプロセスなんですけど、そこで目が養われるわけですよね。そのプロセスを踏んでいると、時間がかかるけれど、自分も納得できるんですよね。
——時間をかけることでしか、体得できなかったり、見えないもの、伝わらないものがあると
だから今は、やっぱり基礎固めなんだろうなと思ってます。とにかく自分の根っこに水をやる時間。
カリフォルニアだけでなく、東北や北海道にも以前から興味があって、5年くらい前から少しずつ通っているんですね。根を生やしてみたい地域があって。この状況ですからしょっちゅうは行けないですけど、気をつけながら、今年も行きました。ただ、カリフォルニアの16mmのプロジェクトを最終的にどういう形でまとめようかと考えている最中ですから、両方同時にスタートはできないんです。
だから、岩手と青森に行ったんですけど、機材も持って行ってないんです。向こうの知り合いの家にウェットスーツとロングボードを置かせてもらってるんで、身体ひとつで行って。次に行く時には、自分の感覚を確認しながら、機材を持って行ってみようかなとも思ってますが、とにかく時間をかけながらじっくりやりたい。特にコロナ禍によって、時間をかけるってことの重要性は増しているんじゃないかな。

覚悟と情熱、それをどう積み上げるか
——人との関係性を築く、という意味でも、時間をかける重要性は増していると思われますか? 自身のプロジェクトの強度は、時間によって培われていくと。
そう思います。要は、どれだけ覚悟して、どれだけ情熱を持って取り組めるかってことに尽きるんじゃないかな。好きなことやし。みんな、簡単な方に行きがちだけど、見たらあからさまなやつあるじゃないですか。これはただもんじゃないで! ってすぐにわからされてしまうもの。あからさまに、使っている時間とか、プロセスとか、その人が積み上げてきたものが伝わってしまう作品を観ると、なるほどなと。それが情熱になるっていうか。あ、そうやんなって、自分が作るモチベーションになるんですよ。
クルマの中で暮らすのだって、20年間は、たぶん誰もやらないだろうなと思うんですよ。できないじゃなくて、やらない(笑)。アメリカでも数年の人はいるんです、でも10年過ぎたら、アメリカでも「おおっ」て言われるレベル(笑)。20年やったら誰かなんか引っかかるんちゃうかなって。
『THE SURFER`S JOUNAL』っていう憧れの雑誌に、写真を始めて5年目のタイミングでポートフォリオを持って行ったんです。でも編集長は3秒くらいでパーっと見て、センキューで終わり。そこで「10年が引っかかる必要年数」みたいな話をされたんです。「10年は飽きずにやってくれ」と。
その時に「モノクロで、60年代と同じ機材で、今を写しているんやで」って、こちらは話しているのに、「カラーの写真はないのか」って言われて。目標変えなあかんのかなって帰りの車の中で思ったりもしたんですけど、20年続けているような人がポートフォリオを持ってくる雑誌なんだから、5年の自分に時間をくれたんやなと思うと、すごいモチベーションになったんですよ。
それが20年経って、回り回ってチャンスが来て写真を大きく掲載してくれた。「5年目に持って行ったんですよ」って編集長に話したら、「覚えてるよ」って言ってました(笑)。
——時代のトレンドに合わせる必要はなく、むしろ自分を貫く方に価値がある。
ええ、やっぱり自分の主題というか、人にはストライクゾーンがあるんです。それをやり続ける。20年間やり続けたら、追従する人いないですから(笑)。『THE SURFER`S JOURNAL』からも「君たちのような熱心な写真家なしではTSJ成り立たない」っていうような手紙が来ましたけど、それはとても名誉なことだなと思ってます。やっぱり物を作るっていうことは、日常を自分がどう過ごすか。いい加減に過ごしたらいい加減になる。そこにこだわっているとかではなくて、そういう生き方しかできないんですよ、僕は。

カリフォルニアで写真撮っていると、変な連中ばっかりで、面白いエピソードが転がっているんですよ。まともな人に会う方が少ないくらい(笑)。それらをどう映像にしていくか、ただ「すべらない話」にするんじゃなくて、映像でどう伝えていくかって考えているんです。そこに昔のタイプライターで打つシーンを混ぜたりしたら、僕がこだわってきたサーフィンの黎明期である60年代と繋がっていくんですね。その空気みたいなものは、16mmが持つ人間らしさでなければ映せないと思っているんです。
ただノスタルジーに陥るのではなく、かといってトレンディにするのでもなく、今に合わせたものを撮りたいと思っています。
竹井達男
サーフフォトグラファー。大阪府出身。南カリフォルニアにあるPalomar Collegeで写真を専攻。1999年に卒業し、帰国したのち、2009年からカリフォルニアでのバンライフを開始。おもに南カリフォルニアでサーファーたちを撮影し、日本やアメリカのメデイアで写真を発表している。2018年に写真集『AUTHENTIC WAVE』を出版。
HP: tatsuotakei.com
Instagram: @tatsuo_ takei
Photo by Tatsuo Takei Text by Toshiya Muraoka