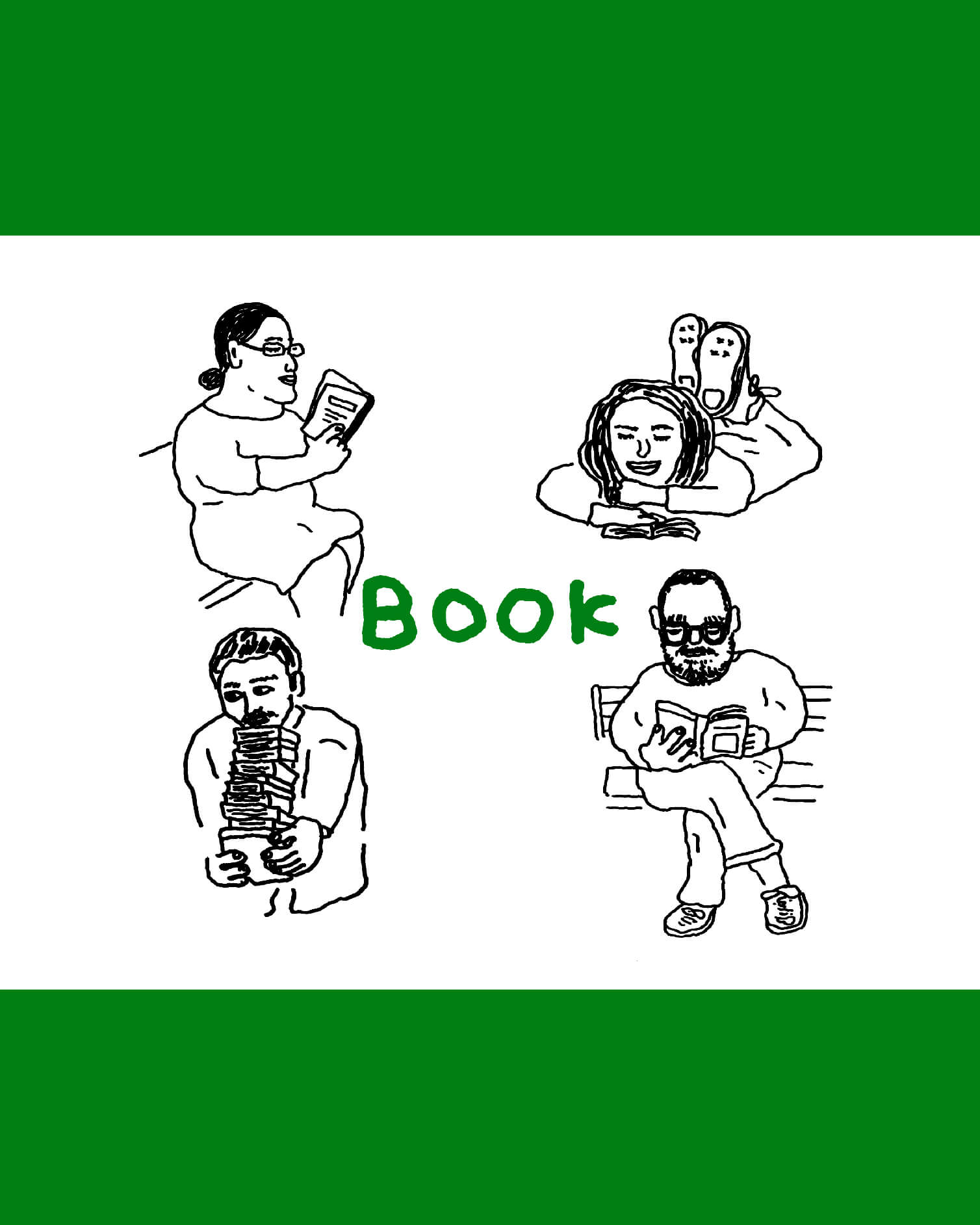「トレンドの波をどう乗りこなすか」を意識していた10代
生まれも育ちも神奈川で、学生時代はバスケに熱中していました。ファッションや音楽が好きで、当時海老名に〈mathematics〉っていうセレクトショップがあったんですが、よく入り浸ってましたね。メインは洋服なんですけど、他にもファッションに付随した音楽だったり、いろんなカルチャーシーンが詰まっているお店で。ちょうど雑誌『relax』が全盛期でその影響もあって、カルチャーの流れだったりトレンドの波をどう乗りこなすか、みたいなことを意識していました。何を着るかっていうよりは、どんな情報を仕入れているか、みたいな。お金もなくてほしい服も買えなかったし、だけどオレらはそれを情報として知っているぜ、みたいなところでアイデンティティを誇示していた。そんな10代でした。その後〈mathematics〉は厚木に移転したんですが、未だに行きますよ。ずっと先頭を走っているお店じゃないでしょうか。

アパレル中心の3階部分は、ウッドデッキのオープンテラスが広がり、BARエリアも併設されている。
唯一採用してくれたレストランバー。
直感的に自分の人生を賭けてみようと思った
高校でアメリカへ行って、卒業しました。日本に帰ってきたものの大学にも興味なかったんで、とりあえず働こうと40ヶ所ぐらい受けたけど、全部ダメだったんですよ。唯一受かったのが、横浜の海岸通りにある〈amazon club〉っていうレストランバーでした。面接に行った場所がもともと貿易に使われていたという倉庫で、1階をガレージ、2階と3階をテナントにしていて、サンドバックが置いてあったり、働いている人たちみんなの趣味の部屋みたいな雰囲気があって。働いている人もみんなかっこよくて衝撃受けたし、ここに自分の人生を賭けてみようって直感的に感じたんです。僕を面接してくれたナガシマさんっていう方がカリスマ的な人で、その後も色々と影響受けましたね。今でも師匠と呼べるような人です。

23歳の頃、次は音楽の方に行きたくなってレーベル会社に転職しました。だけど、自分が好きなアーティストばかり担当できるわけではない。当たり前なんですけれど、それで嫌になってしまって。当時の社長と話し合って、担当しているアーティスト1組もらって独立しました。音楽フェスを主催するようにもなったのもこの頃です。
ところが、だんだん音楽業界の未来に疑問を抱き始めて。アーティストたちを見ても、メジャーにいくほど窮屈になっていくし、インディーズでやっていると食えてない。イベントの形にしても、音楽だけに頼っていたら今後は厳しいんじゃないかなって思い始めていました。なので、この時期は音楽だけじゃなくて、とにかくいろんなことやりましたね。ギャラリーやったり、レストランやったり。イベントも本当に様々やりました。

吹き抜けとなる店内1階には、イートインで飲食ができるスペースも併設される。
クリエイティブの父との出会いを経て
『太陽と星空のサーカス』をスタート
渋谷で小さなレストランをやっていたとき、お客さんで映像ディレクターの菊池久志さんが来てくれていたんです。もう音楽はいいやって思っていた時期だったんですが、話していたら意気投合して「おまえ、おもしろいから復帰したほうがいいよ。一緒にイベントやろうよ」って言ってくれて。菊池さんは安室奈美恵とか青山テルマのPVを手がけている人で、インディーズの世界にいた僕に、逆に興味をもってくれたのかもしれません。そういうきっかけがあって、菊池さんと2人で音楽ライブや映像、マルシェなどを融合させたイベント『太陽と星空のサーカス』をスタートさせました。それまで僕はメジャーを毛嫌いしていたけど、菊池さんと組むことでメジャーとインディーズのバランスみたいなのをとれるようになりました。30代に入ってからの僕のクリエーションは菊池さんの影響がものすごく大きいですね。クリエイティブの父だと思っています。

2階部分にはテントやイス、ランタン、カバンなどアウトドアギアがズラッと並ぶ
後に「太陽と星空のサーカス」を題材にした映画も作って、そのストーリーに出てくる舞台をリアルに再現したいねっていうことで、〈一番星ヴィレッジ〉というキャンプ場をプロデュースすることになりました。そのうち、菊池さんがそろそろ映像に専念したいっていうことになり、同じタイミングで僕も離れることにしました。『太陽と星空のサーカス』では、メジャーなものの力を見せつけられましたね。大きな商業施設と組んで、まわすお金の規模も変わりましたし。僕自身は美大出身でもないし、そういうのを勉強してきたわけではないですけれど、気づいたらクリエーションだったりプロデュースなんかをしていて。大きなターニングポイントになりました。

2017年〈Purveyors〉をオープン。
影響を受ける側から、あたえていく側へ
『太陽と星空のサーカス』で全国行脚していく中で、自然とアウトドアブランドとの接点が増えていったんです。彼らとの交流をもっと濃いものにしたいっていう思いがあって、2017年に〈Purveyors〉をオープンしました。今は小売としても成り立ってきたし、レストランも始めたばかりですけど安定してきていて。どんなお店になっていくかっていうのは、何とどう出会うかっていうタイミング次第だと思いますね。2020年からは、新たにクラフトビールの醸造所を立ち上げる準備をしてきて、それもいい醸造士との出会いがあったからですし、〈Purveyors〉がこういう店になっているのも今のスタッフが一緒に作ってくれているからこそ。ここ2、3年でスタッフに”僕イズム”が踏襲されてきた感じがありますね。僕はもうお店では掃き掃除ぐらいしかしてない(笑)。
これまで〈amazon club〉のナガシマさんや、菊池さんと出会って影響を受けてきたけど、ここにきて僕が人に影響をあたえていくっていう立ち位置になれたのかなと思っています。

クルマで日本全国走ってみて、桐生が一番良かった
よく聞かれるんですが、もともと僕は桐生にゆかりがあったわけじゃないんです。〈st company〉(桐生・高崎のセレクトショップ)の社長の環さんがよく渋谷のレストランに食事に来てくれていたんですが、その縁でお店に訪れたのが最初。直感的に気に入りましたね。町としては完全に廃れていたけど、絶対デザインし直せるなって思ったんです。文化もちゃんと残っているし、東京からもそれほど遠くない。それに、桐生は渡良瀬川を渡らないと中心街に入れないんですが、川を渡りながらこういう規模感でこういうデザインの街なのかってすぐに頭に入ってくる。把握できるぐらいのコンパクトさっていうところにとても惹かれました。後ろに山があってフィールドも近いし、いい町だなと。
実はこのお店オープンする前、クルマで日本全国走ったんです。結果、桐生が一番でした。


桐生に店をオープンして、東京との2拠点生活になりました。やってみたら、何かとベースはどっちかになきゃだめだなと思うようになって。だから今は東京がベースで、桐生の家に関しては別荘感覚なんです。だからあえて森の中にぽつんとある家を借りて、朝は鳥の声で目がさめるっていう環境にしていて。桐生の家には自分の好きな物ばかり置いているんですよ。東京の家はもう家族におかされているっていうか、僕の居場所なんてないようなものなんですけれど(笑)。3年半かけてなんとなくそういうバランスになってきました。

オーナー小林さんの愛車は、三菱製のジープ。76年式のJ36だ。
ブルワリーにレストラン、
町や人との接点をモチベーションに
お店は醸造所ができたことで、また変わるでしょうね。とにかく、街との新しい接点が生まれたのが嬉しいですね。〈Purveyors〉は東京の方のお客さんがほとんどで、地元のお客さんって少ないんですよ。でもレストランができて、ここにブルワリーができて、っていうので、少しずつ流れが変わってきて。2020年に醸造機を揃えるためにクラウドファンディングで資金を募っていたとき、地元の77歳のおじいちゃんが直接お店に入ってきて、8,000円置いてってくれたんですよ。「年金生活だからお金ないんだけれど」って。その時は感動しすぎて表現できなかったんですけれど、後になって泣けるぐらいグッときて。精一杯の気持ちを受け取って、ちゃんとおいしいビールつくらなきゃなって思いましたね。僕らの最高齢のお客さんですよ。そういう人との接点が生まれたっていうことがとにかく嬉しかった。桐生に来て一番良かったなと思えた瞬間でした。今は、あのおじいちゃんと再会するのが楽しみですね。

2021年2月18日に店舗の1階部分、路面店としてオープンするビール醸造所『FARCRY BREWING』。FARCRY(ファークライ)とは、遠い誰かを思い郷愁に駆られる様や、初めて見た景色・稜線から現れる日の出や日の入りを見たときの心の内を描写した造語なのだそうだ。写真提供:Purveyors
Purveyors(パーヴェイヤーズ)
群馬県桐生市仲町2-11-4
TEL: 0277-32-3446
HP: http://purveyors2017.jp/
ONLINE STORE: https://purveyors2017.com
Instagram: @purveyors2017
Facebook: https://www.facebook.com/purveyors2017/
FARCRY BREWING & CAFE(ファークライ ブルーイング アンド カフェ)
群馬県桐生市仲町2-11-4(Purveyors 内)
TEL: 0277-32-3446
HP: https://farcrybrewing.jp/
Instagram: farcry_brewing
Photo by Shinji Yagi Text by Ryo Muramatsu