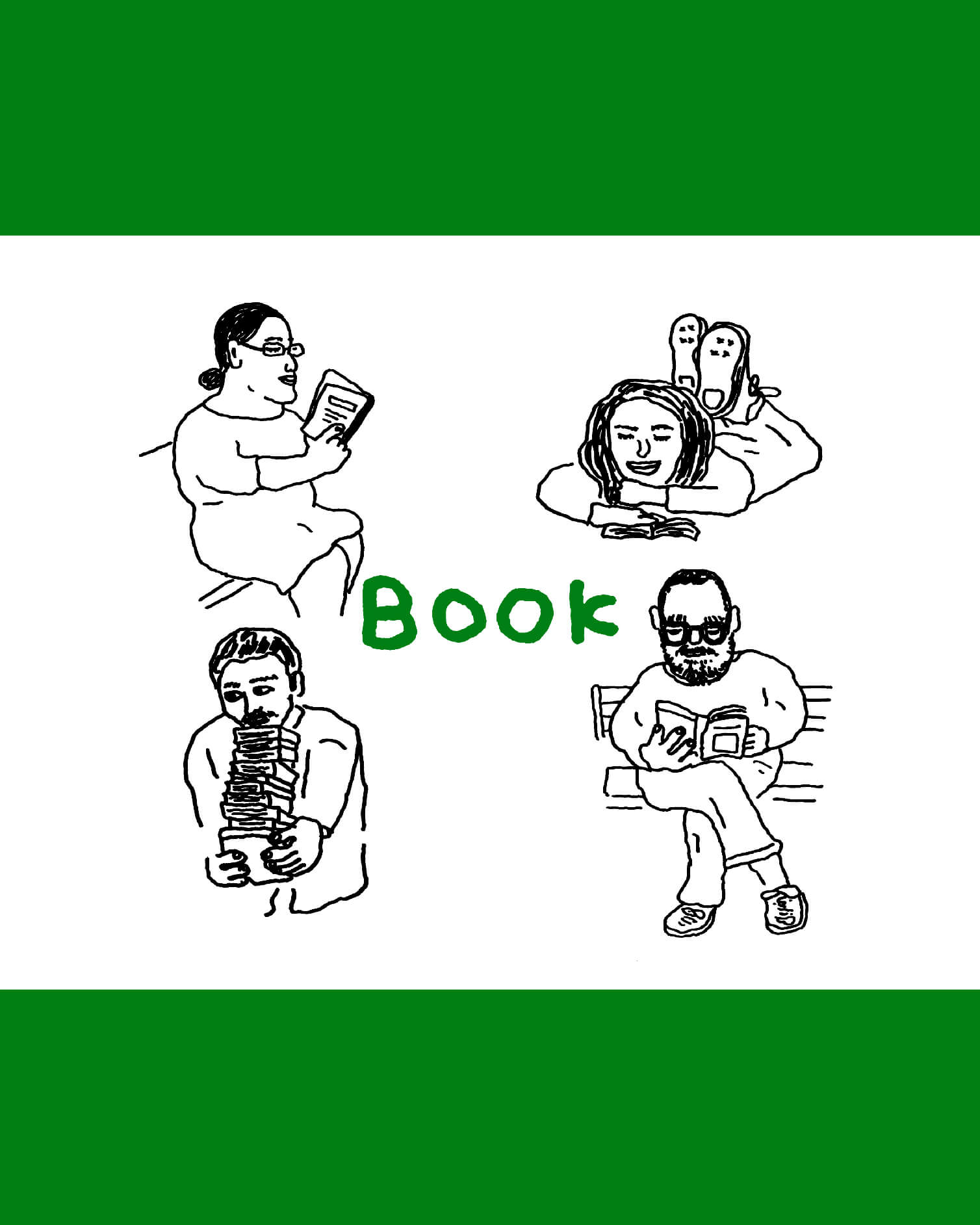フィルムからガラスへ。なくなるなら、自分で作ってしまえばいい
––今坂さんが用いている「湿板(しっぱん)写真」という写真技法は、簡単に言うと被写体をフイルムではなく、ガラスに焼き付けるという、幕末に日本に伝わった撮影手法。特徴のひとつとしては長期間の保存に耐えられるということで、実際に100年以上前に撮影された湿板写真が世界中に現存しています。そもそも、どんなきっかけで湿板写真をやろうと思ったんですか?
写真をはじめて20年以上になりますけど、その頃からデジタルにはそこまで興味が持てなくて、ずっとフィルムをメインに撮ってきました。でも、だからと言って古典技法に固執しているわけでもなくて、むしろ常に自分にとっての新しい表現みたいなものを模索しています。そんな中で、取り組みたい表現のひとつとして湿板写真があった。4、5年前から少しずつリサーチやテストを重ねて、備品などを揃え始めていたんです。
––発売したばかりの写真集『Wet Land』は、ちょうどコロナ禍に撮影された作品をまとめたものですが、湿板写真の制作を本格化したことと、パンデミックは何か関係しているんですか?
コロナによって制作活動が加速したのは事実ですが、どちらにしても湿板写真にはいずれ辿り着いていたと思います。



写真集『Wet Land』(美術出版社)
––というと?
そもそも現実的にフィルムの価格高騰は続いていますし、フィルムの数自体も少なくなっています。写真というメディアを選び、表現活動しているアーティストとして、これは死活問題です。この状況に身をまかせても仕方がないですし、納得いく表現を続けていくためには、フィルムに代わるものを自分で作ってしまえばいいんだと考えました。湿板写真であれば、ガラスを用意して、薬品を自分で調合すれば、既製品のフィルムに頼ることなく写真を撮り続けることができます。実際に、印画紙も数少なくなっていますけど、ガラスのネガからデジタルに転換することもできるので、限りなく既製品に頼らない表現を生み出せると思ったんです。
––なくなるなら自分で作ってしまえばいいってことですね。
そうですね。あとは美術館なんかに行くと、100年以上前のガラスのネガが残っていて、そのもの自体がとても美しいんですよ。写真のネガであるということ以前に、物質として綺麗だったことも惹きつけられるひとつだったと思います。割れたらなくなってしまう、その物質的な儚さは、デジタル全盛の時代へのアンチテーゼでもありますし。
––今坂さんは普段ニューヨークを拠点に活動していますが、現在は湿板写真用のガラスや薬品をカスタムメイドで作っていると聞きました。湿板写真用のガラスや薬品の既製品は、日本国内と比べてもアメリカは選択肢が多いと思うのですが、なぜわざわざカスタマイズされているんですか?
一番で綺麗に焼き付く方法を突き詰めていったら、カスタメイドのものに至ったと言う感じです。だから結果論ですかね。確かに既製品もたくさんありますが、それだとやっぱりどこかありきたりのものになってしまう。本当に自分がほしいコントラストや透過率を実現するにはオリジナルで作ったものが一番しっくりくるんです。

『Wet Land』製作時のワンシーン
––古典的な撮影手法ではあるけれど、現代の技術やセンスみたいなものが加わって新しい表現の形になっているんですね。
ニューヨークで何やってるの?ってよく聞かれるんですけど、作品を撮ることはもちろんですけど、常に新しいテストをしているんです。納得できるまで試して、あるレベルを越えたら、これを使って作品を撮ろうっていうのがいつもののプロセスなんです。


『Wet Land』製作風景。自作の暗室ボックスや湿板写真用のガラスなど。
コロナ禍での気づき。物質的なものの価値の揺れ戻し
––先ほど「コロナ禍で湿板写真の制作が加速した」と話していましたが、それはどうしてでしょうか?
コロナによって、世界的にデジタルのコミュニケーションが普及したのは事実ですが、僕はそのカウンターとして、より物質的なものの価値も高まったと思っています。例えば、zoomのようなオンラインミーティングのツールが当たり前にものになったことによって、人とのコミュニケーションにおいての、表情の小さな変化や言葉と言葉の微妙な間といったものの大事さを僕自身、改めて気がつく機会になりました。
––より物質的な表現に興味が湧いたんですね。
そうですね。湿板写真というのは、ガラスがあって、薬品を人の手で塗る。どうしたって誰かの痕跡が写真に残るんです。撮影の前日はガラスを1枚、1枚磨く作業もあるんですよ。
––以前、湿板写真の撮影現場に立ち会ったことがあるんですが、シャッターを切ってすぐにスタジオ内に簡易的に作った暗室で、職人さんたちが現像作業をしていました。今坂さんは撮影から現像までの一連の作業をご自身とアシスタントの2人でこなしているんですよね。しかもロケ撮影となると、森の中というようなシチュエーションで現像作業を行うわけですが、これってかなり大変なことですよね?
そうですね。ロケで湿板写真を撮影するために、暗室もモバイル型の持ち運べるタイプのものを自作しているんです。撮影してすぐに小さな暗室ボックス内で、ガラスに現像液をかけ、あとは水洗いします。現場で乾燥まではやりきれないので、画像が焼き付いたガラスを水につけたまま持ち運べるタンクの中に一枚ずつ入れて、次の場所に移動するんです。最後にスタジオや宿に戻って、水洗をし直して、乾燥させます。現場では、1カットを撮影するのにテストからタンクにガラスを入れるまでだけでも、大体1時間くらいはかかりますね。
––それだけのプロセスを経て撮影する写真は、フィルムで撮る写真と何が違うんでしょうか?
シンプルに、自問自答する時間が増えているかもしれません。何が撮りたいんだろうか、本当にこれでいいのだろうか、と。それと、作業が雑になると写真に露骨に出てしまう、というのも大きな違いかもしれません。撮影してすぐに小さな暗室ボックス内で、ガラスに現像液をかけるんですけど、そこでうまくガラス全体に液が広がらなければ、液だれができたり、画像が映ってないところができたりするんです。僕は、ヒューマンエラーが作品の一部にもなる、とも考えているので、よくアシスタントに「上手に失敗してよ」って言ったりしていますけど(笑)。


『Wet Land』(2021)
写っていないけど、写っているもの。『Wet Land』に込めた想い
––今回の作品集『Wet Land』には、2021年に撮った作品の中から76点を収録していて、中には先ほど話したようなヒューマンエラーのある、いわゆるミスショットも選んでいるんですよね。これにはどんな意図があるんですか?
現像液がうまくのらなかったりして、画像がでてこない部分がある写真には、ある種の「身体性」みたいなものが宿っているとも考えていて。
––「誰かの痕跡」という話ですね。
それと、湿板写真は紫外線写真なので、可視光線ではなくて、自分たちの目に見えてない紫外線に反応しているんです。だから露出なんかも少し間違えただけで真っ暗になって、目の前にあるのにも関わらず写らないんです。そういった現像時のミスだったりも全部さらけ出すことで、鑑賞する人がその「誰かの痕跡」みたいなものを少しでも感じとってくれたり、「写っていないけど写っているもの」を想像してくれたりしたら、写真との新しいつながりが持てるのかもしれないなって思っているんです。
––想像力を掻き立ててる余白というか、敢えて違和感みたいなものを残しておくという感じなんですね。
作品からはそんなイメージは湧かないかもしれませんが、実は多くの人が行き交う場所で撮影していることもあるんです。ですが、どの風景写真も長時間露光で撮影しているので、人が歩いていてもほとんど写らないんです。決して美しい風景写真を撮ろうと思っているわけでなくて、むしろ僕的には人間も撮っている。みんな忙し過ぎて、写らないだけで。早く歩きすぎなんです。そういう自分たちの物差しでは測れない時間の流れを捉えたいし、湿板写真はそれを捉えることができる撮影手法なのだとも思っているんです。

今坂庸⼆朗 (いまさかようじろう)
1983年、広島県⽣まれ。⽇本⼤学芸術学部を卒業後、2007年に渡⽶。ニューヨークのプラットインスティテュートでMFAを取得し、現在ニューヨークのブルックリンを拠点に活動。これまでに欧米を中心にミネアポリス美術館、パリフォト、Miyako Yoshinagaギャラリー等での個展やグループ展で作品を展示。作品はニューオリンズ美術館、サンノゼ美術館、ミネアポリス美術館、カーネギー美術館等のアメリカ主要美術館に多数収蔵されており、また複数のプライベートコレクションに収蔵されている。2022年に自身初となる日本での個展「Wet-Land」をGINZA SIX内にあるTHE CLUBギャラリーで開催、同年秋、イタリアを代表するファッションブランド〈FENDI〉とのコラボで原宿・表参道に大型アートワークを飾るなど近年日本を始め、アジアでも積極的に活動の幅を広げている。
2023年10⽉20⽇に写真集『Wet Land』(美術出版社)を発売。
HP https://yojiroimasaka.com
IG @yojiroimasaka
photo: Yojiro Imasaka / text: Ryo Muramatsu